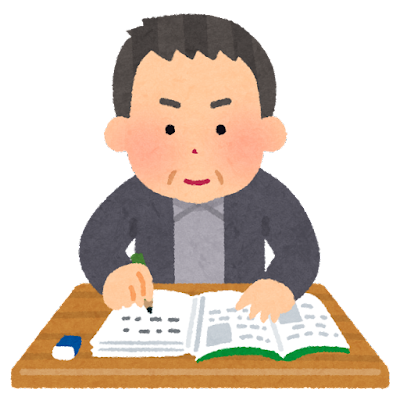初めまして、このブログの管理人の町草と申します。
町草は両耳に重度の感音性難聴を抱えていて、補聴器を付けなければほぼ何も聞こえません。
今回のテーマは、「聴覚障害者になると勉強で何が問題になり学習方法はどうすればいいのか?」となります。
健聴者からすると、耳が聞こえなくなっただけなのだから普通の人と変わらないのでは?と思うかもしれません。
しかし、聴覚障害者になると、勉強においてもかなりのハンディキャップが出て来ます。
それがなぜなのか?を解説し、それでも負けずに勉強する方法をご紹介します。勉強が苦手で仕方ないという聴覚障害者なら、今回の記事を読めば勉強好きになりますよ!
聴覚障害者になると勉強でどんな問題が出る?

管理人が人生を振り返ってみると、聴覚障害者になってから勉強で出て来た問題は以下の通りになりました。
- 先生の声がほぼ聞き取れないので、授業に付いていけなくなった
- 何か学びたくてもどこかの教室に通う事が困難
- 英語など外国語はどうしてもできないことが出てくる
- いじめなどで過剰なストレスを受けて、勉強しても頭に入らない時期があった
- 勉強への意義が分からずモチベーション上がらない
学校では授業を受けますが、管理人の場合は感音性難聴という病気でしたので補聴器を付けても先生の声が聞き取れなくなりました。
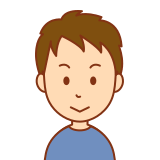
感音性難聴は耳の奥にある蝸牛という、音を聴神経に流すため電気信号に変える部分に問題が出た病気です。
適切に電気信号に変換できないので脳が理解できず、補聴器を付けても相手の声が聞き取れなくなってきます。
先生からは「黒板を見ればいい」と言われますが、黒板だけの内容だと情報量が少なすぎて理解できません。
かといって教科書を読んでいると、今度は「先生の方を見なさい!」と怒られる。そういう状況でしたので、当時はどんどん勉強嫌いになっていきました。
先生の声が聞こえないという事は、学校だけでなくどこかの教室に通っても同様ですね。ですから、何か学びたくても、どこかに通うといったことが難しくなります。
英語やドイツ語など外国語は努力ではどうしようもなく、どうしても出来ないことが出て来ます。
この聴覚障害者が外国語を学ぶときの問題点については、以下の当ブログ別記事で詳しく書いたのでご覧ください。
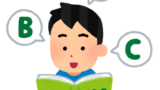
その出来ないことは、ヒアリングとスピーキングです。この2つはお手本を聞いて、発音を覚えてその通りに発音することが必要となります。
ところが、聴覚障害者はお手本が聞き取れないので、ヒアリングとスピーキングはできません。
中学時代ですが、同級生の一人に平気で暴力を振るう子がいてかなりいじめられました。その時は頭が真っ白になって、勉強しても記憶できない考えられないといった症状が出て大変でした。
後から知ったのですが、記憶に関わっている脳の部位に海馬というところがあります。この海馬はストレスに弱く、過剰なストレスを受けると小さくなって段々と物覚えが悪くなるという症状が出ます。
これは、つらい出来事を記憶しないようにする脳の仕組み。
また、過剰なストレスがかかると、思考などを担当している前頭全皮質の機能が止まってしまうので考えられず理解力も落ちます。
こちらは、今は危険だから考えずにすぐ逃げろという脳からのシグナルだそうです。
正直に言えば、われわれのような障害者はいじめのターゲットになりやすいし出来ないこともあるので普通よりもストレスを抱えやすいでしょう。ですから、他の人も似たような状況になる可能性があります。
最後に上で書いたような状況が続いたところ、どれだけ偏差値が高い高校に入っても同じだと考えてモチベーションがまったく上がりませんでした。
このように聴覚障害者だと、いろいろな問題が出てきて勉強でもハンディキャップがあります。
どうしても勉強は独学が中心になってしまう

健聴者なら何か学びたいことが出来たら、どこか教室を探して習いに行くでしょう。
しかし、聴覚障害者は上でも触れたように、先生の声が聞こえないのでどうしても独学が中心になってしまいます。
こう言うと独学では限度があるので、深く学ぶことはできないと落ち込む人もいるかもしれません。
でも、安心してくださいね。
現在(2021年11月)では、家に居ながらその道のプロから学ぶこともできますし独学でも全然問題ありません。
しかも、お金もほとんど掛かりませんよ!
どこかの教室に通うなら学ぶジャンルにもよりますが、毎月数万円くらいは掛かるケースもあるでしょう。それが、月数千円になり場合によっては無料で学ぶことも可能です。
本当なの?と困惑するかもしれませんが、具体的には下の「聴覚障害者が独学する方法」に詳しく書いたのでご覧ください。
聴覚障害者が独学する方法
耳が聞こえない人が独学するなら、どんな方法があるでしょうか。その方法を、こちらにまとめたので、参考に勉強を進めていきましょう。
とにかく本や教科書を読み・覚えて・理解する
勉強の基本は以下の3つです。
- 勉強したいジャンルの本で分かりやすいものを探して読む
- 本の中から覚えておきたいものをノートに書き写す
- ただ機械的に覚えるのではなくちゃんと理解できているかチェック
勉強とは既にあるものを取り入れることですから、読み・覚えて・理解するが基本となります。
ですから、何を勉強するか決まったら、まずはそのジャンルの本でおすすめは何があるか調べることから始めます。
なお、これが学校なら教科書となりますが、それだけだと理解できないところもあるので参考書には何があるか調べましょう。
選ぶコツは最初は専門書など難易度が高いものを選ばずに、分かりやすいと感じる本を選ぶことです。
正直に言えば最初から分厚い専門書を選んでも、難しすぎてすぐ読まなくなって挫折するだけです。
分かりやすい方の本を読んでみて、もっと学びたいと感じてから専門書を買いましょう。
本を読んでいると、ここは覚えておきたいという所が出てくるでしょう。その箇所を、ノートに書き写してください。書き写したら、何度もノートを読み返して覚えましょう。
なお、覚えたい箇所があれば、本に赤ペンや蛍光ペンで線を引くやり方もあります。でも、本に直接書くと、読むたびに何度もページを探す手間があるのでノートに書き写した方がおすすめです。
最後に覚えたことを、ちゃんと理解しているかチェックしましょう。機械的に覚えても、しばらくすれば忘れてしまいます。しかし、理解していることは、忘れにくいのでずっと覚えておくことができます。
これは、理解しているならその周辺の情報も一緒にくっついて情報量が多くなっているので、思い出しやすく忘れにくくなるためです。
本を読むのが苦痛で全く読めないときは?
聴覚障害者の勉強は、基本的に本を読んでいくことです。でも、本を読むのが苦痛で、全く読めないという方もいらっしゃるかもしれません。
そういう人は、できるだけ読みやすくページ数も短いものを選び1~2時間ほどで集中して一気に読んでみてください。
毎日少しずつ読むと前日に読んだ内容を忘れてしまうため、理解度がどうしても低下してしまいます。そのため、思い切って1~2時間ほど用意して、一気に読んだ方が理解しやすくなります。
この時に、本の内容をすべて理解しよう記憶しようと考えないことです。そして、覚えるべきところや理解できないところは、ノートなどに書き写して後で繰り返し読んで理解・覚えましょう。
聴覚障害者がポモドーロテクニックを使うには?
勉強に集中したい時は、タイマーをセットし25分集中して5分休憩するポモドーロテクニックが有効です。ところが、聴覚障害者はタイマーの音が聞こえないので、一般的なキッチンタイマーなどは使用できません。
かと言って、スマホのバイブ機能を使うと目に入った途端にメールチェックやネットサーフィンをしたくなってしまいますね。
おすすめは、タニタから販売されているバイブレーションタイマーを使うか、スマートウォッチを使う方法です。
タニタのバイブレーションタイマーは、終了のお知らせを振動で行ってくれるので聴覚障害者も使用することができます。
バイブレーションタイマーについては、当ブログの以下の記事で細かくレビューしています。

もう一つ、管理人はMiスマートバンドというスマートウォッチを使用していますが、こちらもカウントダウンタイマー機能があり終了は振動でお知らせしてくれるので助かっています。
Youtubeを使えば無料で勉強ができる
本も良いですが、Youtubeを使うことで無料で勉強することも可能です。近年では様々な分野のプロの方が、一般向けに自分の専門のことを解説している動画が増えています。
これはYoutubeには再生数などに応じて、投稿者にお金が入る仕組みがあるからです。
視聴するだけなら無料で利用できるので、今学んでいるジャンルでプロが解説している動画がないかチェックしてみましょう。
なお、Youtubeには字幕生成機能がありますが、動画によっては使えないばかりか字幕自体の精度が低くて利用できないケースがあります。
この場合は、以下の方法を使えば読み取れる可能性があります。
- 音声認識アプリであるUDトークをインストールしたスマホ・タブレットを置いて視聴する
- タブレットmimiを置いて視聴する
どちらも、音声を読み取って文字に変換して画面に表示してくれる機能があります。つまり、自動的に字幕を生成してくれるので耳が聞こえなくても動画の内容が分かるようになります。
UDトークは30分までと制限がありますが、無料で使えるのでスマホやタブレットがあればぜひ試してみてください。
タブレットmimiの方は、ソースネクスト社が販売している聴覚障害者サポートツール。電源を入れれば、後は置いておくだけで周りの人の声を拾ってどんどん文字に変換してくれます。
なお、音声を拾う関係上、音を出していないとダメですが、耳が聞こえないと適切な音量が分からずに騒音問題になることがありますのでご注意ください。
聴覚障害者に習い事って意味はある?

個人的な見解ですが、症状が重くほぼ聞き取れない人でも現在ならサポートする機器を使えば習い事も無駄にならないと思います。ただし、物理的に不可能なケース、例えば聞き取りができないのに外国語の発音を覚えるとかは無理ですよ。
聴覚障害者が問題になるのは、聞こえないことで情報が入って来ない、意思伝達が難しくなる点です。
しかし、上で紹介したような音声認識アプリや機器を使えば、聞こえない問題は大体クリアできるでしょう。
例えばスポーツなら、UDトークなどインストールしたスマホかタブレットmimiなどを指導者に渡しておく。何か伝えることがあれば、スマホやタブレットmimiを通じて伝えれば大丈夫でしょう。
逆に座学が中心となる習い事なら、机を一番前にしてもらいタブレットmimiを置いておく。そうすれば、後はタブレットmimiが先生の声を拾って文字に変換してくれるので何を話しているのか分かるようになります。
UDトークの場合は、無料版だと30分の制限があるので有料バージョンを使うことになります。ただ、スマホはメールが来るなどで集中力に影響があるので、音声を文字に変換するしかできないタブレットmimiの方が良いでしょう。
なお、タブレットmimiの公式ページは下のリンクより行くことができます。レンタルもできるので、気になったらぜひ試してみてください。
また、タブレットmimiの詳細なレビューは、当ブログの以下の記事をご覧ください。

独学で勉強するのに役立つ本・サービス
最後に、独学で勉強するのに役立つ本・サービスをご紹介します。
独学で勉強するなら、1冊は持っておきたいのが「独学大全」です。本の読み方が分からない、勉強が続かない、論文の読み方が分からないなど、独学していてこういった時どうする?を適切な技法と共に紹介してくれます。
なお、700ページを超えるので全部読む必要はなく、必要なところだけを読むと良いでしょう。
読書が嫌い、本を読むのが苦痛で全然読めないという人は、ぜひ読んで欲しい1冊。本が苦痛だという人は、実はある考え方が原因です。本書はその困った考えを吹き飛ばしてくれ、読書が楽しくなる方法が書かれています。
なお、遅読家のための読書術は、当ブログの以下の記事にレビューがあります。

勉強するなら本をたくさん読むのが一番ですが、本って結構高いので出費がかさみますよね……。
出来るだけ出費を抑えたいなら、管理人も加入しているKindle Unlimited(キンドル アンリミテッド)がおすすめです。
意外と勉強に役立つ本が揃っていて、電子書籍ですが月額980円で読み放題となっています。
どんな本が読み放題になっているのか、例を挙げれば……。
などがあります。(上の例は2021年11月5日現在の場合で、時期によっては終了している可能性があります。)
普通に購入すれば2000円以上はする本も、Kindle Unlimitedに含まれています。980円なら本1冊くらいの値段なので、それだけで読み放題になるなら本代をかなり節約できますね。
下のバナーから、Kindle Unlimitedのページへ飛べるのでご活用ください。
まとめ
聴覚障害者の勉強に関して、どんな問題が出てくるのか?聞こえなくてもどう勉強すればいいのかまとめました。
我々は耳が聞こえないことから、従来は人から教わることができないなど勉強でもハンディキャップを抱えていました。
ところが、現在(2021年)ではそういった勉強のハンディキャップはほとんどなくなっています。
UDトークといった無料で使える音声認識アプリや、有料ではあるものの文字を可視化してくれるタブレットmimiなど聴覚障害者を助けてくれるものがたくさん出て来ました。
また、現在では昔とは比べものにならないくらい本がありますし、ネットで検索すればすぐに情報が集まると勉強に適した環境です。
こういった道具や環境を最大限に活用して、耳が聞こえないハンディキャップを吹き飛ばしましょう!